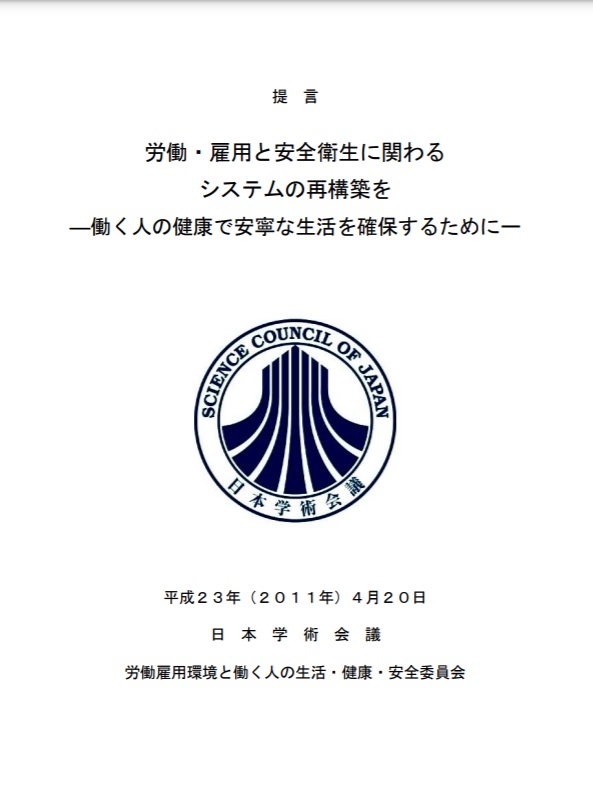政府が、9月末、学術会議から推薦された会員候補105名の中で、人文・社会系6名の任命を拒否したことが明らかになりました。このニュースを聞いて、「新内閣は、学術会議をどう考えているのか」という疑問とともに、従来の政府自身の立場からも大きく外れた、信じられない任命拒否に対する憤りの思いが強くなってきました。
菅首相は息苦しい独裁国家を目指すのか?
歴代内閣は学問の自由を尊重してきた。任命拒否は瀧川事件などを想起させる歴史的暴挙!
困難な状況に直面し、時代が大きく変わろうとする今こそ、多様で自由闊達な議論が必要だ!!
日本学術会議人事への内閣による介入に抗議します
詳しい経過については、新聞報道や国会審議を通じて徐々に明らかになってきました。そして、菅首相は、記者会見ではなく、「インタビュー」なるもので、「総合的、俯瞰的な活動を確保する観点から判断した」と述べただけです。重大な任命拒否をして、その明確な理由を示さないことはきわめて重大な問題です。どう考えても「任命拒否」自体が異常なことであり、その具体的理由を明らかにすることが必要です。
1983年学術会議法の改正で、会員選出が従来の「選挙制」から、会議の推薦に基づいて首相が任命する「任命制」に変わりました。その際に、この「任命制」について、政府自身が「形式的任命」に過ぎないという解釈を示してから、その解釈に基づく運用が40年近く継続してきました。
ところが、与党議員などから、逆に、学術会議自体の在り方を問題にする議論も出ています。そうした議論の中で、下村博文議員(自民党政調会長、元文科相)が「学術会議は、政府に対して2007年を最後に正式な『答申』を出していない」と指摘したというニュースに「あまりに事実とかけはなれた指摘をするものだ」と驚かされました。この下村発言については、広渡清吾・元学術会議会長が、「政府からの諮問がなかったので答申をしていないだけで、どんどん諮問してもらえば答申を出す」と反論をされています(10月9日)。
既に、海外のマスコミや世界的な学術雑誌から、日本政府の学問の自由への抑圧的姿勢に批判的な記事が出ています。この問題は、単なる政治的な問題ではなく、日本政府、日本社会の基本的あり方にかかわる重大問題だと思います。
私自身も、学術会議が実に多様な問題できわめて活発な活動を展開して、多くの積極的な提言をしてきたことを直接に経験してきました。
その一つが、日本学術会議「労働雇用環境と働く人の生活・健康・安全委員会」の「提言 労働・雇用と安全衛生に関わるシステムの再構築を―働く人の健康で安寧な生活を確保するためにー」(2011年4月20日)
という提言書です。
この委員会は、岸玲子委員長(医学・北大)、和田肇副委員長(法学・名古屋大学)を中心に、医学、法学、経済学など多分野の会員、連携会員、特任連携会員22名が、2009年4月から2011年4月までの2年間に、シンポジウムなどの集まりをもつ一方、18回もの委員会審議して、40頁、4万3千字におよぶ大部の提言書をまとめたのです。
この文書は、結論として、
(1) 国の健康政策に「より健康で安全な労働」を位置づけるとともに社会的パートナーである労使と協力して安全衛生システムの構築
(2) 労働・雇用および安全衛生にかかわる関連法制度の整備と新たなシステム構築
(3) 事業主および労働者、関係諸機関に求められる取り組み
の三つを提言しています。
この(2)の中で、次のように、過労死防止の法的整備を挙げていることは大いに注目すべきことです。
①過重労働と過労死・過労自殺を防止するための法的な整備を行う
国は、過重労働対策基本法を制定し、過重労働対策の基本を定め、過重労働に起因する労働者の健康被害の実態を把握し、過労死・過労自殺等の防止を図る。36協定などの制度を見直し、1日の最長労働時間、時間外労働の時間についての1日、1週、1月、1年単位での上限を設定し、併せて最低休息時間制度を導入し、時間外労働等の賃金割増率を引き上げるべきである。また、ILO第132号条約の批准を目指し、最低2労働週の連続休暇の取得を推進するための諸条件の検討を開始すべきである。
特筆すべきは、Asu-netの代表でもあった森岡孝二・関西大学経済学部教授(当時)が、「特任連携会員」として、この委員会に参加し、シンポジウムや提言書をまとめるのに大きな役割を果たしたことです。森岡さんは、学術会議が刊行する月刊誌『学術の動向』(2010年10月号)〔特集 雇用労働環境と働く人の健康・生活・安全〕に、「働く人々の労働時間の現状と健康への影響」という論文を掲載されています。
※私自身は、この提言書作成に直接関与していませんが、提言書作成に加わった連携会員が中心となった公衆衛生学会の分科会で、「非正規雇用と健康」に関連する報告を担当するなど、間接的に「参加」しています。脇田滋「労働法、社会保障法再構築の課題」矢野榮二編『非正規雇用と労働者の健康』(労働科学研究所出版部、2011年5月)参照。
この2011年提言書は、学術会議として、文系・理系を超えた総合的かつ俯瞰的な視点から、過労死防止ためには法的整備が必要であることを訴えたのです。この提言は、学術界だけでなく、経済社会、さらには、政府や国会にも大きな影響を与えました。そして、議員立法という形で「過労死防止法」(正式名「過労死等防止対策推進法」)案が国会で審議され、2014年6月20日、与野党を超えた全会一致の賛成で成立したのです(2014年法律第100号)。
過労死防止法制定には、「過労死家族の会」や「過労死弁護団」など市民・法律家団体が、長年にわたる取り組みで中心的な役割を果たしました。本来であれば、労働組合が先頭になって労働者を守る役割を担うべきですが、企業別労組が多い日本の労働組合では、過労死防止で目立った活動をした組合は多くありません。総論では過労死防止を叫んでも、過労死を実際に防ぐために必要な人員増や、労働時間の大幅短縮に取り組むことは、企業別単位組合では容易ではないからです。そして、企業間競争を理由にギリギリの人員で過密労働を強いる労務管理に労働組合として対抗できず、この大きな壁を打ち破れずにきました。
本来は、個別企業の劣悪労働環境を改めるのには、「総資本の理性」を体現すべき政府が、過労死防止の法的整備の主体になってもおかしくありませんでした。しかし、政府自らが、長年にわたって新自由主義的な規制緩和政策を進め、労働時間規制の柔軟化など、過労死が広がる環境を逆に拡大する方向を追求してきました。また、過労死をめぐる行政訴訟で政府は、被告として過労死家族や弁護団と対峙してきました。そうした事情からも、内閣提出法案として、過労死防止法案を提出することが難しかったのかもしれません。
しかし、過労死の問題は、もはや日本の雇用社会、さらには日本社会そのものを根底から崩壊させるほど深刻な状態に達していました。経営側としても、大切な社員を過労で失うことは大きなマイナスであることは明らかなのに、個別経営者、さらには経営者団体として過労死を無くすための積極的方針を出すことができないままでした。ただ、一部の「ブラック経営者」でない限り、まともな理性のある経営者であれば、過労死防止に反対できないはずです。
そうしたときに、日本学術会議が、理系・人文社会系の枠を超えた学術研究者集団として、総合的、俯瞰的、科学的な提言をしたことは、過労死防止法制定への時宜にかなった、大きなバネの役割を果たしたのだと思います。政府としては、自ら姿勢を改めることは容易ではありません。政府機関ではあっても、「独立性」が強い日本学術会議であるからこそ、それまでの労働法規制緩和政策の基調とは大きく異なる提言書を出すことができたのです。
学術会議は、残念ながら、世間的には余り知られていない地味な組織かも知れません。しかし、その「改革」を言うのであれば、学術会議が創設された歴史的経緯を改めて再確認することが重要です。第2次大戦前、学問の自由、大学の自治が侵害され、無謀な戦争に至った歴史的経緯を振り返ることが必要です。
現在的には、政府から独立した学術研究者の集団として、日本学術会議が多くの提言によって果たしてきた重要な役割を正確に見る必要があります。そうした視点無しに、「改革」の名目で根底から変えようとする議論は、余りに乱暴です。強く反対せざるを得ません。
とくに、働き方の関連では、学術会議が、労働法規制緩和を進める政府とは独立した立場から、過労死防止などの方向を示した提言と、その意味を改めて見直すことが必要だと思います。ILO(国際労働機関)は、ディーセントワーク(Decent Work)の実現、つまり、働く人が人間らしく働き暮らせる社会を目ざしています。日本では政府が進めてきた労働法の過度な規制緩和によって、雇用社会の劣化が深刻です。こうした状況だからこそ、真の働き方改革のために、政府からの独立性を堅持した日本学術会議のさらなる活動の発展こそが必要なのです。
人間らしい働き方を目指す労働法研究者として、また、働き方Asu-netの一員としても、今回の、日本学術会議人事への内閣による介入に強く抗議します。
〔付言〕
「総合的、俯瞰的」という用語について一言
「総合的、俯瞰的」の「俯瞰」は、辞書によれば、「鳥瞰」と同義で、「高い所から見下ろし眺めること」を意味するとされています。つまり、上から下を見下ろす「鳥の目で見る」ということです。
しかし、鳥のように上空から下を見るだけでは、現実のすべてが見えるわけではありません。むしろ、鳥が見ることができない、落ち葉の下で蠢(うごめ)く「虫の目」で社会の実態をみることが重要だという趣旨で、私は、かつて「虫瞰(ちゅうかん)的」現実認識の重要性を強調したことがあります。
「職場の現実から目をそらさない虫瞰的(ちゅうかんてき)現実認識の意義 派遣労働の現実 労働法のない世界」(労働法律旬報No.1485(2000年8月上旬号)p.4-5)
政府が進める政策にとって都合の悪い事実について、政府はその実態を調査などで明らかにしません。その一つが、派遣労働者(非正規雇用労働者)の実態でした。政府統計や政府調査だけに頼るのではなく、労働法研究者として積極的能動的な実態認識(=虫瞰的認識)が重要だという趣旨です。
私は、研究者には「総合的、俯瞰的かつ虫瞰的な視点」が必要だと思っています。